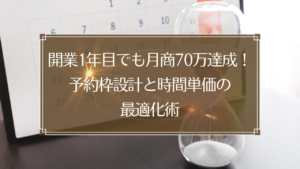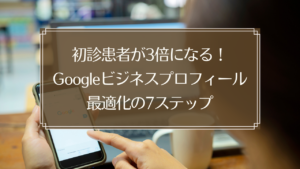【鍼灸院の経営】施術メニュー表のデザイン術!患者の選択率を40%上げるレイアウト5原則
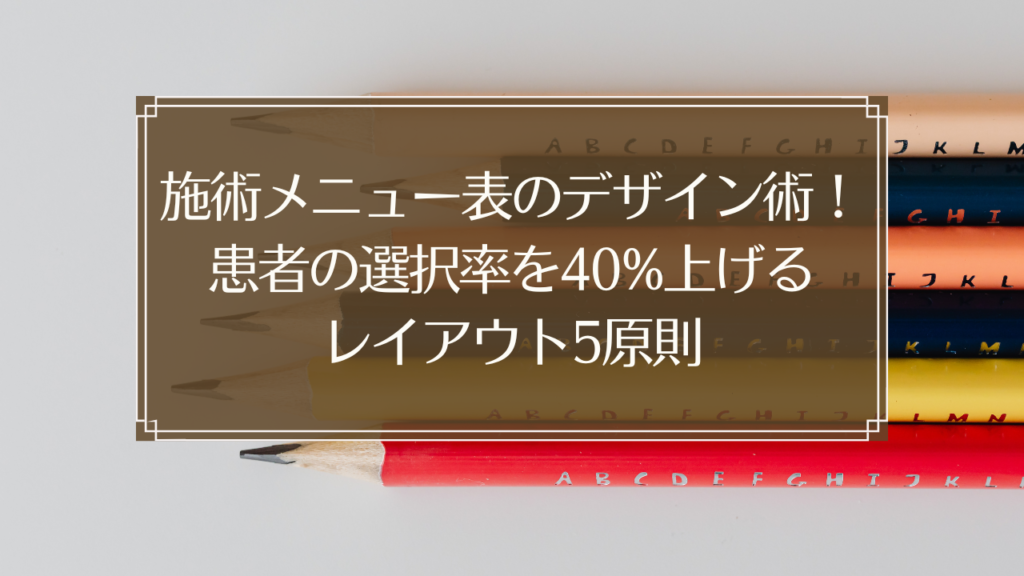
こんにちは!鍼灸院の経営塾‐AMG‐代表の宮崎圭太です。施術メニュー表を作ったのに、患者さんがいつも同じ基本メニューばかり選んで、高単価メニューに目を向けてくれないとお悩みではありませんか?🤔
「メニューが多すぎて選べない」「どれが自分に合っているか分からない」と患者さんが迷っている間に、あなたの院の売上機会は失われています。
実は、メニュー表のデザインとレイアウトを変えるだけで、患者さんの選択率は40%以上アップするんです。このブログでは、心理学とマーケティングの視点から、患者さんが「これを選びたい!」と直感的に思えるメニュー表の作り方を5つの原則で徹底解説します。
このブログを読めば、明日からすぐに実践できるメニュー表改善のノウハウが手に入り、高単価メニューの成約率が上がって売上アップにつながりますよ!
目次
- 施術メニュー表で患者の選択率が低い3つの原因
- メニュー表デザインが売上に与える影響とは
- 患者の選択率を40%上げるレイアウト5原則
- 各原則を実践する具体的テクニックとツール
- メニュー表を継続的に改善するPDCAサイクル
- まとめ:明日から実践できるメニュー表改善アクション
施術メニュー表で患者の選択率が低い3つの原因
情報過多で患者が選べない状態になっている
多くの鍼灸院で見かけるのが、メニューが10個以上並んでいる状態です。
「肩こりコース」「腰痛コース」「美容鍼コース」「全身調整コース」「骨盤矯正コース」「産後ケアコース」…とずらりと並んでいると、患者さんは圧倒されてしまいます。
これは心理学で「選択のパラドックス」と呼ばれる現象です。選択肢が多すぎると、人は決断できなくなってしまうんですね。
さらに、専門用語ばかりの説明文も問題です。「経絡の調整」「気の流れを整える」「自律神経のバランス」といった言葉は、私たち鍼灸師にとっては当たり前でも、患者さんには難しく感じられます。
結果として、患者さんは「よく分からないから、とりあえず一番安いので…」と基本メニューを選んでしまうんです。
視線誘導が設計されておらず推奨メニューが目立たない
メニュー表を見るとき、人の目は一定の法則で動きます。
一般的には、左上から右上へ、そして左下から右下へと「Z」の形で視線が動く「Zの法則」や、上から下、左から右へと「F」の形で動く「Fの法則」が知られています。
しかし、多くの鍼灸院のメニュー表では、すべてのメニューが同じ大きさ、同じフォントで縦に並んでいるだけ。これでは、どのメニューが推奨なのか、どれを選べばいいのかが全く分かりません。
せっかく高単価メニューや専門コースを用意しているのに、視線が行かない位置に配置されていたら、もったいないですよね。
デザインにおいて、「見せたいものを見せたい順番で見てもらう」という視線誘導の設計は非常に重要なんです。
価格表示が患者の心理的抵抗を生んでいる
価格の見せ方ひとつで、患者さんの心理的ハードルは大きく変わります。
例えば、「¥8,000円」と表示するより「8000円」と表示する方が、心理的な抵抗が少ないと言われています。「¥」マークや「,」カンマは、お金を支払うことを意識させてしまうからです。
また、価格だけが目立っていて、その施術の価値や効果が伝わっていないのも問題です。「高い」と感じるのは、価格と価値のバランスが取れていないからなんですね。
さらに、比較対象がないと、患者さんは「これが高いのか安いのか」が分かりません。1つのメニューだけを提示されても、判断材料がないわけです。
価格表示の心理術!患者が「高い」と感じない料金設定と伝え方のコツも参考にしてみてください。
メニュー表デザインが売上に与える影響とは
AMGメンバーの事例を元にしたメニュー表改善の効果
AMGのある鍼灸院では、メニュー表のリニューアルで大きな成果を上げました。
その院では、以前は12個のメニューが縦に並んでいて、価格と施術時間だけが記載されている状態でした。高単価の専門コースもありましたが、選択率はわずか25%程度。
そこで、メニューを5つに絞り込み、視線誘導を意識したレイアウトに変更したんです。
具体的には以下の改善を行いました:
- 推奨メニューを中央上部に大きく配置
- 写真とアイコンで視覚的に分かりやすく
- 「おすすめ」のラベルを追加
- 価格表示を「1回あたり○○円」に変更
- 施術の効果とベネフィットを明記
その結果、高単価メニューの選択率が42%まで上昇し、客単価も1.6倍にアップしました😊
メニュー表のデザインを変えるだけで、こんなにも結果が変わるんです。
メニュー表は無言の営業マンである
メニュー表は、あなたに代わって患者さんに価値を伝える「営業ツール」です。
口頭で説明する場合、施術者によって伝え方が変わったり、説明漏れがあったりします。でも、メニュー表がしっかり作り込まれていれば、誰が対応しても同じ質の情報を提供できるんです。
これは、鍼灸院経営における「標準化」という観点でも非常に重要。将来的にスタッフを雇用する場合でも、メニュー表があれば教育がスムーズになります。
また、患者さんは家に帰ってからメニュー表を見返すこともあります。その時に「次はこのコースを試してみよう」と思ってもらえれば、リピート率アップにもつながります。
メニュー表は、一度作ったら終わりではなく、継続的に改善していく「営業資産」なんですね。
患者の選択率を40%上げるレイアウト5原則
原則1:視線誘導の原則
人の視線は、無意識のうちに一定のパターンで動きます。
Zの法則は、左上→右上→左下→右下と、アルファベットの「Z」を描くように視線が動く法則です。チラシやポスターなど、一枚の紙面でよく使われます。
Fの法則は、上から下、左から右へと「F」の形で視線が動く法則。縦長のメニュー表やウェブページで有効です。
この法則を活用すると、推奨メニューを「左上」または「中央上部」に配置することで、自然と患者さんの目に留まるようになります。
さらに、推奨メニューだけを少し大きく、太字で表示することで、視線を誘導できます。
「見せたいものを見せたい順番で見てもらう」という意識を持つだけで、メニュー表の効果は劇的に変わりますよ!
原則2:情報量のバランス原則
メニューは3~5個に絞るのが最適です。
前述した「選択のパラドックス」を避けるためにも、患者さんが迷わずに選べる数にすることが大切なんです。
「でも、うちは症状別に色々なメニューがあるから…」という声が聞こえてきそうですね。その場合は、大分類を3~5個にして、小分類を折りたたむ形で構成しましょう。
例えば:
- 基本コース(初めての方・肩こり・腰痛)
- 専門コース(産後ケア・スポーツ障害・自律神経)
- 美容・リラクゼーション(美容鍼・全身調整)
このように大分類で整理すると、患者さんは自分に合ったカテゴリーを選びやすくなります。
詳細情報は必要最低限にして、「もっと知りたい方はスタッフにお尋ねください」と誘導するのも良い方法です。
顧客心理を活用した施術メニューの作り方も参考になりますよ。
原則3:価格の心理的見せ方原則
価格表示には心理学のテクニックが隠されています。
松竹梅の法則というものをご存知ですか?3つの選択肢があると、人は真ん中を選びやすいという心理現象です。
例えば:
- 松:プレミアムコース 12000円
- 竹:スタンダードコース 8000円(おすすめ!)
- 梅:ベーシックコース 5000円
このように並べると、多くの患者さんは真ん中の「竹」を選びます。高すぎず安すぎず、バランスが良いと感じるからです。
また、アンカリング効果も活用できます。最初に高価格のメニューを見せることで、その後に出てくる価格が相対的に安く感じられる効果です。
価格表示の工夫としては:
- 「¥」マークやカンマを省略する(8000円)
- 「1回あたり○○円」と表示して心理的ハードルを下げる
- 回数券やコースの場合は「総額÷回数」で単価を見せる
コース料金設定術!単価を2倍にしても患者が納得する価格戦略も併せて読んでみてください。
価格と価値のバランスを見せることで、「高い」という印象を「価値がある」に変えられます。
単価アップにつながる!施術メニューの組み合わせ提案テクニックも参考になります。
原則4:ビジュアル活用の原則
文字だけのメニュー表より、写真やイラストがあると理解度が格段に上がります。
視覚情報は文字情報の6万倍のスピードで脳に届くと言われています。だからこそ、ビジュアルを活用することで、患者さんの理解と共感を得やすくなるんです。
具体的には:
- 施術風景の写真:どんな施術を受けるのかイメージしやすい
- イラストやアイコン:症状や効果を視覚的に表現
- Before/After写真(可能な場合):効果の実感を伝える
色彩心理も重要です。色には人の感情に働きかける力があります:
- 青色:信頼感、安心感、落ち着き
- 緑色:癒し、リラックス、健康
- オレンジ色:温かみ、親しみやすさ、活力
鍼灸院のメニュー表なら、青や緑を基調にすると、患者さんに安心感を与えられます。
院内POP制作術!患者の目を引く手書き看板で来院率を2倍にするデザインテクニックも参考にしてください。
原則5:行動喚起の原則
メニュー表には、患者さんに「次のアクション」を促す仕掛けが必要です。
マーケティング用語で「CTA(Call To Action)」と呼ばれるもので、具体的には:
- 「おすすめ」ラベル:どれを選べばいいか迷っている人への指標
- 「初回限定」「人気No.1」:限定性や社会的証明で選択を後押し
- 予約QRコード:その場でスマホからすぐ予約できる
- 「詳しくはスタッフまで」:会話のきっかけを作る
これらの要素を適切に配置することで、患者さんの行動を促せます。
メニュー名も重要です。「腰痛コース」より「デスクワークで疲れた腰を楽にするコース」の方が、患者さんの共感を得やすいですよね。
施術メニュー名変更だけで単価1.5倍!患者心理を活用したネーミング戦略7つの法則も併せてチェックしてみてください。
各原則を実践する具体的テクニックとツール
視線誘導を実現するレイアウトテクニック
視線誘導を実現するための具体的なレイアウトテクニックを紹介します。
推奨メニューの配置:
- A4縦のメニュー表なら、上部1/3のスペースに配置
- 周りに余白を作って目立たせる
- 背景色を変えるか、枠で囲む
フォントサイズの使い分け:
- メニュー名:16~20pt(推奨メニューは22~24pt)
- 説明文:10~12pt
- 価格:14~16pt(大きすぎても小さすぎてもNG)
余白の活用:
余白は「空いているスペース」ではなく、「視線を誘導するための重要な要素」です。情報を詰め込みすぎず、適度な余白を保つことで、読みやすさが格段に向上します。
具体的には、各メニュー間に1行分の余白を入れるだけでも、見やすさが変わりますよ。
情報整理のための3ステップ
現在のメニューを整理して、選びやすくするための3ステップです。
ステップ1:現在のメニューを全てリストアップ
まずは、今提供しているメニューを全て書き出しましょう。症状別、施術内容別、価格帯別など、どんな分類でも構いません。
ステップ2:患者ニーズ別に分類
リストアップしたメニューを、患者さんの視点で分類し直します。
例えば:
- 初めて来院される方向け
- 慢性的な痛みに悩む方向け
- 美容・リラクゼーション目的の方向け
- 産後ケアや女性特有の悩み向け
このように、患者さんが「自分のための」と感じられる分類にすることがポイントです。
ステップ3:優先順位をつけて3~5個に絞り込む
最後に、メイン表示するメニューを3~5個に絞ります。選ばれなかったメニューは削除するのではなく、「その他のメニュー」として小さく記載するか、口頭で説明する形にしましょう。
価格表示の具体的な工夫例
価格表示の工夫で、心理的ハードルを下げる方法を紹介します。
松竹梅の配置例:
【プレミアムコース】12000円
全身の不調を根本から改善
60分 + カウンセリング15分
【スタンダードコース】8000円 ★おすすめ★
気になる箇所を集中ケア
45分 + カウンセリング10分
【ベーシックコース】5000円
初めての方・お試しに最適
30分 + カウンセリング5分「1回あたり○○円」表示:
回数券やコースメニューの場合、総額だけでなく「1回あたり」の価格を併記することで、心理的ハードルが下がります。
例:
5回コース 35000円(1回あたり7000円)
※通常1回8000円のところ、1000円お得!比較表の活用:
複数のメニューを横並びで比較できる表を作ると、違いが一目で分かります。
| 項目 | ベーシック | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 施術時間 | 30分 | 45分 | 60分 |
| カウンセリング | 5分 | 10分 | 15分 |
| 価格 | 5000円 | 8000円 | 12000円 |
| こんな方に | 初回・お試し | 継続ケア | 根本改善 |
無料で使えるデザインツール紹介
デザインの知識がなくても、無料ツールで素敵なメニュー表が作れます。
Canva(キャンバ):
デザイン初心者に最もおすすめのツール。豊富なテンプレートがあり、ドラッグ&ドロップで簡単に操作できます。「メニュー表」と検索すれば、たくさんのテンプレートが出てきますよ。
メリット:
- テンプレートが豊富
- 操作が直感的で簡単
- 無料版でも十分な機能
Googleスライド:
プレゼンテーション用のツールですが、メニュー表作成にも使えます。シンプルなデザインが好みの方におすすめ。
メリット:
- Googleアカウントがあれば無料
- クラウド保存で端末を選ばない
- シンプルで見やすいデザインが作れる
PowerPoint(パワーポイント):
Microsoft Officeをお持ちなら、PowerPointも優秀なツールです。細かい調整がしやすく、プロっぽい仕上がりにできます。
メリット:
- 細かいデザイン調整が可能
- 印刷用のデータとして使いやすい
- テーブル(表)作成が得意
これらのツールで作成したメニュー表は、印刷して院内に掲示するだけでなく、タブレットで表示してカウンセリング時に使うこともできます。
デジタル版なら、料金改定や新メニュー追加の際もすぐに更新できて便利ですよ😊
メニュー表を継続的に改善するPDCAサイクル
メニュー表の効果測定方法
メニュー表は作って終わりではなく、効果を測定して改善していくことが大切です。
各メニューの選択率を記録する:
どのメニューが何回選ばれたかを記録しましょう。簡単なエクセル表やスプレッドシートで十分です。
例:
- ベーシックコース:10回
- スタンダードコース:15回
- プレミアムコース:5回
これを月単位で記録すると、メニュー表変更前後の比較ができます。
患者さんの反応や質問内容をメモする:
カウンセリング時に患者さんが何を質問したか、どのメニューで迷ったかをメモしておきます。これが改善のヒントになるんです。
よくある質問:
- 「このコースとこのコースの違いは?」
- 「初めてだけど、どれがおすすめ?」
- 「このコースは何回くらい通う必要があるの?」
こういった質問が多い部分は、メニュー表の説明が不足している証拠です。
高単価メニューの成約率を追跡する:
特に、高単価メニューの成約率を追跡することで、メニュー表の改善効果が数字で見えます。
成約率 = 高単価メニュー選択数 ÷ 初回来院数 × 100
この数字が上がっていけば、メニュー表の改善が成功している証拠です!
定期的な見直しとブラッシュアップ
メニュー表は定期的に見直しましょう。
3ヶ月に1回の見直しサイクル:
四半期ごとに選択率のデータを見返し、改善ポイントを洗い出します。3ヶ月あれば、十分なサンプル数が集まりますし、短すぎて効果が分からないということもありません。
季節やキャンペーンに合わせた更新:
季節ごとに需要が変わるメニューもありますよね。
例えば:
- 春:花粉症対策、新生活の疲れケア
- 夏:冷房による肩こり、夏バテ対策
- 秋:夏の疲れの回復、免疫力アップ
- 冬:冷え性改善、年末の疲れケア
季節メニューを期間限定で追加することで、新鮮さを保てます。
患者さんの声を反映した改善:
実際に患者さんから「こういうメニューがあったらいいな」という声があったら、積極的に取り入れましょう。患者ニーズに応えることが、選択率アップの近道です。
PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回すことで、メニュー表は常に進化し続けます。小さな改善の積み重ねが、大きな成果につながるんですよ。
まとめ:明日から実践できるメニュー表改善アクション
メニュー表のデザインとレイアウトを変えるだけで、患者さんの選択率は大きく変わります。
今回ご紹介した5つの原則をおさらいしましょう:
- 視線誘導の原則:推奨メニューを目立つ位置に配置して、自然と目に留まるように
- 情報量のバランス原則:メニューは3~5個に絞り込み、選びやすく
- 価格の心理的見せ方原則:松竹梅の法則とアンカリング効果で高単価メニューを選ばれやすく
- ビジュアル活用の原則:写真やイラスト、色彩心理で理解と共感を得る
- 行動喚起の原則:「おすすめ」ラベルやCTAで、次のアクションを促す
明日からできる最初の一歩は、現在のメニュー表を見直すことです。
「情報が多すぎないか?」「推奨メニューは目立っているか?」「価格だけが強調されていないか?」をチェックしてみてください。
AMGメンバーの多くは、小さな改善から始めて、徐々に売上を伸ばしています。一度に完璧を目指さなくても大丈夫。まずは1つの原則から試してみましょう!
メニュー表って、一度作ったら終わりじゃなくて、患者さんの反応を見ながら改善していくものなんです。
初回来院からリピーターに変える接客術のコツ5ステップも併せて実践すると、さらに効果的ですよ。
あなたの鍼灸院が、地域で選ばれる院になるための第一歩を、今日から踏み出しましょう!
AMG公式LINEでは、実際に選択率が上がったメニュー表のビフォーアフター事例や、鍼灸院経営で失敗した事例・成功した事例をもとに、すぐに使える実践的な情報を無料で配信しています。
一人で悩まず、成功している鍼灸院がどんな工夫をしているか、具体的な事例から学んでみませんか?
鍼灸院経営の改善について詳しくはAMG公式LINEにご登録ください