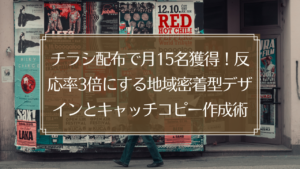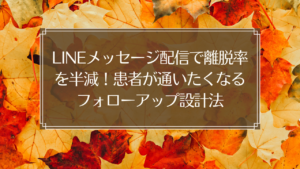【鍼灸院のリピート】カウンセリングシート活用術!患者の本音を引き出す問診項目設計法
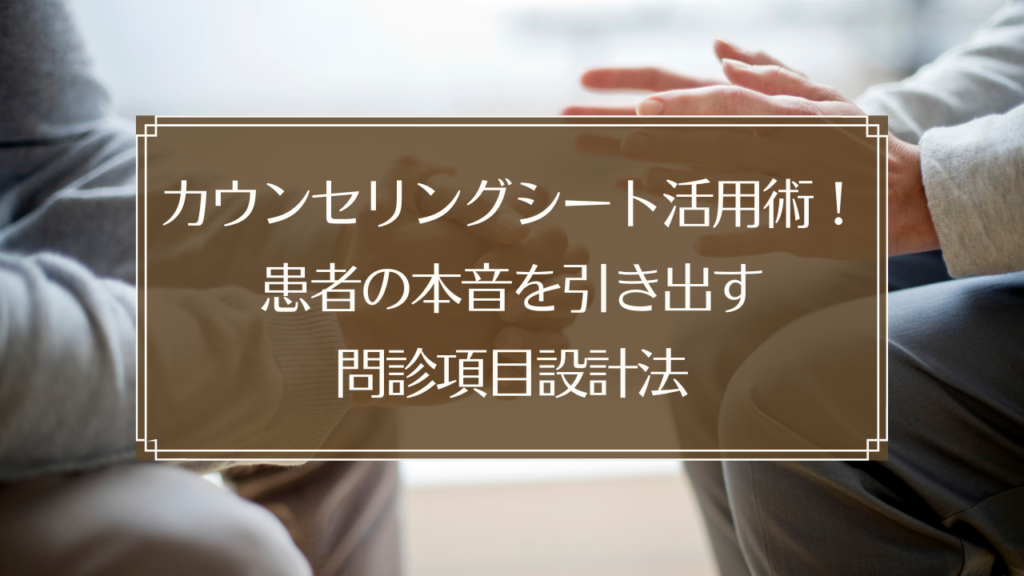
こんにちは!鍼灸院の経営塾‐AMG‐代表の宮崎圭太です。カウンセリングシートを使っているのに、患者さんの本音が引き出せず、リピートにつながらないとお悩みではありませんか?🤔
「問診票を記入してもらっても表面的な情報しか得られない」「どんな質問をすればいいか分からない」「せっかく情報を集めてもリピート率が上がらない」そんな声をよく聞きます。
実は、多くの鍼灸院が使っているカウンセリングシートは「事実を聞く質問」ばかりで、患者さんの本当の願望や悩みを引き出せていないんです。
このブログでは、患者の本音を引き出してリピート率を劇的に向上させる問診項目設計法を詳しく解説します。この方法を実践すれば、患者さんとの信頼関係が深まり、継続率が飛躍的にアップします。
目次
- カウンセリングシートでリピート率が上がらない3つの原因
- AMGメンバーの事例を元にしたカウンセリングシート改善の効果
- 患者の本音を引き出す問診項目設計7ステップ
- 各ステップで使える具体的な質問フレーズ集
- カウンセリングシート作成時の重要なポイント
- カウンセリングシート活用でリピート率を上げる実践法
- まとめ:明日から実践できるカウンセリングシート改善術
カウンセリングシートでリピート率が上がらない3つの原因
事実だけを聞く質問で患者の本音が見えていない
多くの鍼灸院のカウンセリングシートを見ると、こんな質問ばかりなんです。
「どこが痛いですか?」
「いつからですか?」
「どんな時に痛みますか?」
これらは確かに大切な情報です。でも、これだけでは患者さんの本当の願望や悩みは見えてきません。
例えば、「肩が痛い」という訴えの裏には、「子どもを抱っこするのが辛い」「デスクワークに集中できない」「好きなテニスができなくて悲しい」という本音が隠れているんです。
表面的な症状の裏にある「その症状で何に困っているか」「改善したら何をしたいか」という本音を引き出す必要があります。
顧客心理の観点から見ると、患者さんは「痛みをとってほしい」のではなく、「痛みがなくなって○○したい」という願望を持っているんですよね😊
問診項目が多すぎて患者に負担をかけている
「詳しく聞きたい!」という熱意は素晴らしいです。でも、その熱意が裏目に出ることもあるんです。
50項目以上の質問を並べてしまうケースをよく見かけます。記入に15分以上かかると、施術前に患者さんが疲れてしまうんです。
せっかく来院してくれたのに、カウンセリングシートで疲れさせてしまっては、信頼構築どころではなくなってしまいます。
顧客体験設計の視点で考えると、最初の接点で負担をかけると、リピート意欲が下がってしまうんです。
患者さんは「この院、なんだか面倒くさいな」という第一印象を持ってしまう可能性があります。
シートを情報収集だけに使い対話につなげていない
これが一番もったいないパターンです!
記入してもらって終わり、カルテに綴じて終わりでは意味がありません。
カウンセリングシートは「対話のきっかけ」として使うことで、患者さんの本音がさらに引き出せるんです。
「ここに○○と書いてくださいましたが、もう少し詳しく教えていただけますか?」
こんな一言から、患者さんとの深い対話が始まります。
マーケティングの視点で言えば、カウンセリングシートは情報収集ではなく、信頼構築とニーズ把握のツールとして活用すべきなんです。
AMGメンバーの事例を元にしたカウンセリングシート改善の効果
問診項目を見直してリピート率が78%に向上した事例
AMGのある鍼灸院では、カウンセリングシートの問診項目を大幅に見直しました。
「事実を聞く質問」から「本音を引き出す質問」へのシフトです。
変更前のリピート率は45%でした。それが変更後、なんと78%まで向上したんです!
特に効果的だったのは、「症状が改善したら何をしたいか」という質問でした。
この質問により、患者さんの本当の願望が分かり、それに寄り添った提案ができるようになったんです。
例えば、ある患者さんは「肩こり」で来院されました。でも、本当の願望は「孫を抱っこできるようになりたい」だったんです。
この願望を知ることで、施術の価値提案が「肩こりの改善」から「孫との時間を楽しめる体づくり」に変わります。
患者さんにとっての価値が明確になり、継続する理由が生まれるんですよね。
初回カウンセリングの時間配分術!信頼構築から成約率を2倍にする方法も併せて読むと、さらに効果的です。
患者の本音を引き出すことで成約率が2倍になった理由
AMGの別のメンバーは、「施術への期待と不安」を聞く項目を追加しました。
「当院に期待していることは何ですか?」
「施術を受ける上で、不安なことはありますか?」
このシンプルな2つの質問が、大きな変化をもたらしたんです。
患者さんの不安を事前に把握し、カウンセリング時に丁寧に解消することで、成約率が1.5倍から3倍に向上しました。
なぜこんなに効果があったのか?
顧客心理の観点から見ると、不安を解消することが信頼構築と成約の鍵なんです。
患者さんは「痛くないか」「効果があるか」「どれくらい通う必要があるか」など、様々な不安を抱えています。
その不安を先回りして解消してあげることで、「この先生なら安心して任せられる」と思ってもらえるんですよね😊
患者の本音を引き出す問診項目設計7ステップ
ステップ1:基本情報は最小限にして負担を減らす
まずは基本情報を見直しましょう。
必要最低限の項目だけに絞るんです。
必要な基本情報
- 名前
- 連絡先(電話番号、メールアドレス)
- 年齢
- 職業(症状との関連を知るため)
不要な基本情報
- 詳細な住所(請求に必要な場合のみ)
- 家族構成
- 趣味(初診時に不要)
詳細な住所や家族構成など、初診時に不要な情報は聞かないでください。
顧客体験の最適化という視点で考えると、記入負担を減らすことで、本当に大切な質問に集中してもらえるんです。
患者さんは「この院は必要なことだけ聞いてくれる」と好印象を持ちます。
ステップ2:症状の「影響」を聞く質問を設計する
ここが最も重要なステップです!
症状そのものではなく、症状が生活に与えている影響を聞くんです。
従来の質問
- どこが痛いですか?
- いつから痛いですか?
- どんな時に痛みますか?
本音を引き出す質問
- その痛みで、日常生活のどんなことに困っていますか?
- その症状があることで、何ができなくなっていますか?
- 痛みがあることで、我慢していることはありますか?
この質問の仕方を変えるだけで、患者さんが話す内容が劇的に変わります。
「デスクワークに集中できない」
「子どもを抱っこできない」
「好きなゴルフに行けなくなった」
こういった具体的な悩みが出てくるんです。
症状そのものより、患者さんの生活への影響を深掘りすることで、本当の悩みが見えてきます。
ステップ3:理想の未来を描く質問で願望を引き出す
患者さんの本音を引き出す最強の質問があります。
それが「理想の未来を描く質問」です!
効果的な質問例
- 症状が改善したら、どんなことをしたいですか?
- もし痛みがなくなったら、一番やりたいことは何ですか?
- 3ヶ月後、どんな状態になっていたら嬉しいですか?
この質問により、患者さんの本当の願望や目標を引き出すことができます。
マーケティング視点で言えば、顧客の理想の未来を把握することで、価値提案がしやすくなるんです。
「痛みをとる」という機能的価値ではなく、「やりたいことができるようになる」という情緒的価値を提供できるようになります。
患者さんにとって、施術を受ける意味が明確になるんですよね😊
ステップ4:選択式と記述式をバランスよく配置する
質問形式のバランスも大切です。
チェックボックスで答えやすくしつつ、自由記述欄も設けるんです。
選択式(チェックボックス)のメリット
- 答えやすい
- 記入時間が短い
- データ分析がしやすい
記述式(自由記述)のメリット
- 深い情報が得られる
- 患者さん独自の悩みが分かる
- 本音が見えやすい
記述欄には「ご自由にお書きください」ではなく、具体的な質問を添えてください。
NG例
「その他、ご自由にお書きください」
OK例
「この施術を受けることで、3ヶ月後にどうなっていたら嬉しいですか?」
具体的な質問があることで、患者さんは何を書けばいいか迷わず、深い本音を書いてくれるようになります。
回答しやすさと深い情報収集のバランスが取れるんです。
ステップ5:過去の治療歴を「ストーリー」で聞く
過去の治療歴を聞く時、多くの院がこんな質問をしています。
「他院での治療歴はありますか? はい・いいえ」
これだけでは、患者さんの治療への期待や不安、価値観が見えてきません。
ストーリーで聞く質問例
- これまでどんな治療を試しましたか?
- その治療を受けてみて、どう感じましたか?
- 効果があった治療、なかった治療があれば教えてください
- 過去の治療で、嫌だったことや不安だったことはありますか?
このように聞くことで、患者さんの治療への期待や不安、価値観が見えてくるんです。
競合分析の視点から見ると、他院での経験から自院の差別化ポイントが見つかります。
「前の院では説明が少なくて不安だった」→「当院では丁寧に説明します」
「効果を感じられなかった」→「効果測定を重視します」
このように、患者さんの過去の経験を知ることで、自院の強みをアピールできるんですよね。
ステップ6:施術への期待と不安を明確にする
患者さんの期待と不安を事前に把握することは、信頼構築の基本です。
期待を聞く質問
- 当院に期待していることは何ですか?
- この施術でどんな効果を期待していますか?
不安を聞く質問
- 施術を受ける上で、不安なことはありますか?
- 気になっていることがあれば教えてください
これにより、患者さんの心理状態に寄り添った対応ができます。
期待に応え、不安を解消することが信頼構築の基本なんです。
例えば、「痛くないか不安」と書かれていたら、カウンセリング時に「痛みに配慮しながら施術しますので、安心してくださいね」と先回りして伝えられます。
患者さんは「この先生は私の不安を理解してくれている」と安心するんですよね😊
ステップ7:シートを対話のツールとして活用する
最後のステップが、カウンセリングシートを「対話のツール」として活用することです。
記入してもらって終わりではなく、記入内容をもとに深掘りするんです。
対話の例
「ここに『子どもを抱っこするのが辛い』と書いてくださいましたが、具体的にはどんな時に困りますか?」
「『デスクワークに集中できない』とのことですが、どれくらいの時間で痛みが出ますか?」
シートを対話のきっかけにすることで、さらに本音が引き出せます。
カウンセリング技法の実践として、シートに書かれた内容を起点に、さらに深い対話を展開していくんです。
患者さんは「この先生は私のことを本当に理解しようとしてくれている」と感じ、信頼関係が深まります。
初回来院からリピーターに変える接客術のコツ5ステップも参考にしてみてください。
さらに詳しい質問フレーズ集やカウンセリングシートのテンプレートは、AMG公式LINEで無料配信していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
各ステップで使える具体的な質問フレーズ集
症状の影響を深掘りする質問例5選
患者さんの本音を引き出すための具体的な質問フレーズをご紹介します。
これらはコピー&ペーストしてすぐに使えるので、明日からのカウンセリングシートに取り入れてみてください!
質問1:日常生活への影響
「その症状で、日常生活のどんな場面で困っていますか?」
この質問により、患者さんの具体的な困りごとが見えてきます。
質問2:我慢していること
「痛みがあることで、我慢していることはありますか?」
患者さんが諦めていることや我慢していることが分かります。
質問3:仕事・家事への影響
「その症状が仕事や家事に与えている影響を教えてください」
経済的・社会的な影響が見えてきます。
質問4:諦めていること
「その痛みのせいで、諦めていることはありますか?」
患者さんの本当にやりたいことが見えてきます。
質問5:症状がない状態の想像
「もしその症状がなかったら、今と何が変わると思いますか?」
理想の状態を想像してもらうことで、施術の価値が明確になります。
カウンセリング満足度を高める5つの質問技法も併せて読むと、さらに質問力が向上しますよ。
理想の未来を引き出す質問テンプレート
患者さんの願望を引き出す質問テンプレートです。
3ヶ月後の理想
「3ヶ月後、どんな状態になっていたら嬉しいですか?」
具体的な期間を示すことで、患者さんが想像しやすくなります。
一番やりたいこと
「症状が改善したら、真っ先にやりたいことは何ですか?」
「真っ先に」という言葉により、本当にやりたいことが引き出せます。
理想の生活
「痛みがなくなったら、どんな生活を送りたいですか?」
生活全体のビジョンが見えてきます。
なりたい自分
「この施術を受けて、どんな自分になりたいですか?」
アイデンティティレベルでの願望が引き出せます。
これらの質問により、患者さん自身が「施術を受ける意味」を明確に認識できるようになるんです。
施術の価値が明確になり、リピート率が向上します。
患者の価値観が分かる過去の治療歴の聞き方
過去の治療歴を聞く時の具体的なフレーズです。
治療内容を聞く
「これまでどんな治療を受けてきましたか?」
どんな治療を試してきたかを知ることができます。
感想を聞く
「その治療を受けてみて、どう感じましたか?」
患者さんの治療への期待や評価基準が分かります。
効果の有無を聞く
「効果があった治療、なかった治療があれば教えてください」
何が効果的だったかを知ることで、施術方針の参考になります。
ネガティブな経験を聞く
「過去の治療で、嫌だったことや不安だったことはありますか?」
患者さんが避けたいことが分かり、同じ失敗を繰り返さずに済みます。
これらの質問により、患者さんの治療への期待や不安、価値観が見えてくるんです。
その情報をもとに、患者さんに合った施術提案ができるようになります。
カウンセリングシート作成時の重要なポイント
記入時間は5~7分以内に収める設計術
カウンセリングシートは、記入時間が長すぎると逆効果です。
理想的な記入時間は5~7分以内です。
適切な項目数
- 項目数は15~20項目程度に絞る
- 選択式を多用し、記述式は3~5項目に限定
記入時間が長すぎると、患者さんが疲れて本音を書く気力がなくなってしまいます。
顧客体験設計の視点で考えると、最初の接点で負担をかけないことが大切なんです。
「このくらいならサッと書けるな」と思ってもらえる量が理想です。
項目を厳選することで、本当に大切な質問に集中してもらえます。
患者との信頼関係を深める効果的な問診票の作り方も参考にしてください。
読みやすさと温かみを両立するデザインのコツ
カウンセリングシートのデザインも、患者さんの印象に大きく影響します。
フォントの選び方
- 読みやすいゴシック体または明朝体を使用
- 小さすぎる文字は避ける(最低でも10pt以上)
レイアウトのポイント
- 適度な余白を取り、窮屈な印象を避ける
- 項目ごとに区切り線を入れて見やすくする
色使いの工夫
- 温かみのある色使い(パステルカラーやアースカラー)
- 院のコンセプトカラーを取り入れる
ロゴの配置
- ヘッダーに院のロゴを配置
- ブランディングとして統一感を出す
ブランディングの視点で言えば、カウンセリングシートも院の世界観を表現するツールなんです。
「この院は温かくて信頼できそう」という第一印象を与えられるデザインを目指しましょう。
デジタルと紙、どちらが効果的か
カウンセリングシートをデジタルにするか紙にするか、悩む方も多いですよね。
紙のメリット
- 温かみがあり、親しみやすい
- 手書きの本音が引き出しやすい
- 高齢の患者さんでも抵抗なく記入できる
紙のデメリット
- 保管場所が必要
- データ管理が大変
- 後から見返すのが手間
デジタルのメリット
- データ管理が楽
- 記入ミスが減る
- 検索や分析がしやすい
デジタルのデメリット
- 操作に慣れていない患者さんには負担
- システム導入コストがかかる
- 温かみが感じられない場合がある
結論としては、患者層やコンセプトに合わせて選択するのがベストです。
高齢の患者さんが多い院は紙、若い世代が多い院はデジタルという使い分けも効果的です。
業務効率化の視点で言えば、デジタルの方が管理は楽ですが、温かみを重視するなら紙という選択もありです。
カウンセリングシート活用でリピート率を上げる実践法
記入内容をもとに深掘りする対話テクニック
カウンセリングシートに記入してもらったら、それを起点に対話を深めていきましょう。
対話の基本テクニック
シートに書かれた内容を起点に、さらに深掘りする質問をするんです。
「ここに『デスクワークに集中できない』と書いてくださいましたが、もう少し詳しく教えていただけますか?」
「『子どもを抱っこするのが辛い』とのことですが、具体的にはどんな場面で困りますか?」
このように聞くことで、患者さんは「この先生は私のことを本当に理解しようとしてくれている」と感じます。
対話することで、患者さんとの信頼関係が深まるんです。
さらに深掘りする質問例
- 「それはいつ頃からですか?」
- 「それが改善したら、どんな風に生活が変わりますか?」
- 「その症状で一番辛いことは何ですか?」
カウンセリング技法の実践として、シートを対話のツールとして使いこなすことが大切です。
施術後の声かけ革命!患者の心をつかむ魔法の会話テンプレート7選も参考にしてみてください。
シートから患者ニーズを読み取る分析ポイント
カウンセリングシートから、患者さんのニーズを正確に読み取ることが重要です。
分析のポイント
記述式の回答から、患者さんの価値観や優先順位を読み取りましょう。
「痛みをとりたい」と書く人と「趣味を楽しみたい」と書く人では、アプローチが変わります。
「痛みをとりたい」タイプ
- 症状そのものに焦点を当てた説明が効果的
- 即効性や改善の度合いを重視
- 施術の技術面をアピール
「趣味を楽しみたい」タイプ
- 症状改善後の生活に焦点を当てた説明が効果的
- 長期的な体づくりを提案
- 生活の質の向上をアピール
顧客理解を深めることで、一人ひとりに合った価値提案ができるようになるんです。
患者さんのニーズを正確に把握することが、リピート率向上の鍵なんですよね😊
カウンセリング結果を施術提案につなげる方法
カウンセリングシートで引き出した本音をもとに、患者さんのニーズに合った施術プランを提案しましょう。
効果的な提案の例
「先ほど、お子さんを抱っこするのが楽になりたいとおっしゃっていましたね」
「このプランは特に肩の可動域改善に効果的で、多くの方が3回の施術で抱っこが楽になったと感じています」
このように、シートで引き出した本音と施術プランを紐づけることで、提案の説得力が増します。
患者さんは「この先生は私の悩みを理解してくれている」と感じ、成約率が上がるんです。
提案のポイント
- 患者さんの言葉を使う
- 具体的な効果を示す
- 他の患者さんの事例を紹介する
セールスとマーケティングの統合という視点で言えば、カウンセリングで得た情報を施術提案に活かすことで、押し売りではない自然な成約につながります。
自費診療への移行率を高める!施術説明のポイント5選も併せて読むと、提案力がさらに向上しますよ。
実際のカウンセリングシート事例や、患者さんの本音を引き出すトーク例は、AMG公式LINEでご紹介していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
まとめ:明日から実践できるカウンセリングシート改善術
カウンセリングシートは、リピート率向上のための重要なツールです。
このブログでお伝えした内容を実践すれば、患者さんとの信頼関係が深まり、継続率が飛躍的にアップします。
重要なポイントのおさらい
- 「事実を聞く質問」から「本音を引き出す質問」へシフトする
- 症状そのものではなく、症状が生活に与える影響を聞く
- 理想の未来を描く質問で願望を引き出す
- 7ステップの問診項目設計法を実践する
- 基本情報は最小限に
- 症状の影響を深掘り
- 理想の未来を引き出す
- 選択式と記述式のバランス
- 過去の治療歴をストーリーで聞く
- 期待と不安を明確にする
- シートを対話のツールとして活用
- 記入負担を減らし、対話のツールとして活用する
- 記入時間は5~7分以内
- シートをもとに深掘りする対話を展開
- AMGメンバーの成功事例に学ぶ
- リピート率45%→78%への改善
- 成約率2倍への向上
明日からできる具体的なアクション
まずは、現在のカウンセリングシートを見直してみてください。
「事実を聞く質問」ばかりになっていませんか?
1つでもいいので、「本音を引き出す質問」を追加してみましょう。
「症状が改善したら、どんなことをしたいですか?」
この質問を1つ加えるだけで、患者さんとの対話が変わります。
そして、記入してもらった内容をもとに、さらに深掘りする対話を実践してみてください。
カウンセリングシートは、患者さんとの信頼関係を築き、本音を引き出し、リピートにつなげるための大切なツールです。
一人ひとりの患者さんと向き合い、本当の悩みや願望を理解することで、あなたの鍼灸院は地域で愛される存在になります。
2回目来院率90%達成!初回施術後に必ず伝えるべき3つの魔法フレーズも併せて実践すると、さらにリピート率が向上しますよ。
明日からのカウンセリングが、患者さんとの深い信頼関係を築くきっかけになることを願っています!
鍼灸院経営の改善について詳しくはAMG公式LINEにご登録ください